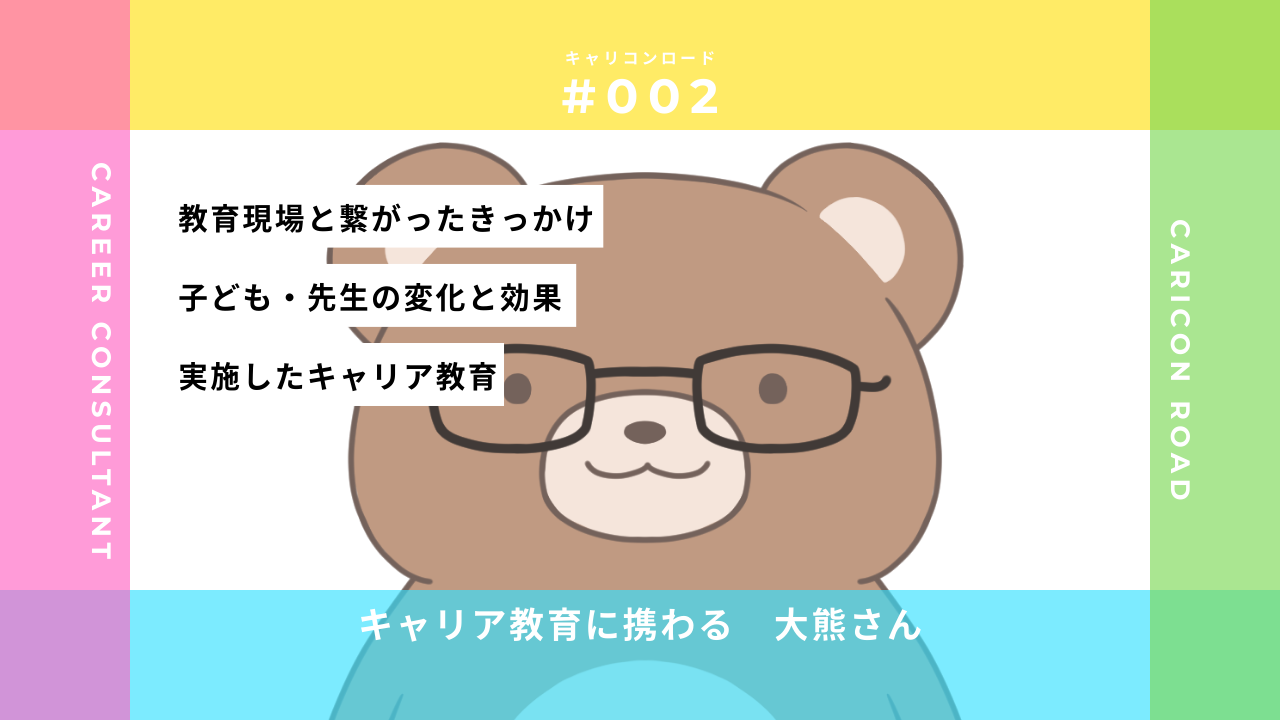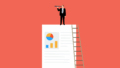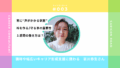キャリアコンサルタントを目指したきっかけ
― よろしくお願いします。まずはキャリアコンサルタントとの出会いと、目指した理由を教えてください。
よろしくお願いします。大熊靖亮(やすあき)と申します。
私は大学卒業後、地元の金融機関に就職したのですが、家庭の事情で会社を5年前に退職したんです。ちょうどコロナが始まった時だったので、社会も一時的に停滞していたこともあり、約1年くらい自己理解を深める中で、「自分は常に人に関わる仕事、人の成長や人の役に立つことを考えて仕事をしてきた」と再認識し、これからは「人に関わる仕事」を中心に活動していこうと決断しました。
正直自分の中で、「自分の経験を活かしながらすぐにできる」と思っていたのですが、よくよく考えてみると人事関連の経験はないし、そもそも本を読む以外で人に関する専門的な勉強をしたことがなかったので、1度しっかり学ぶことも必要だと考えていた時にキャリアコンサルタント資格に出会いました。そこで「この資格は自分が取るべきものだ」と、ビビッと感じ取得しました。
学校・地域とつながった経緯(PTA/学校運営協議会)
― 学校の教育現場とつながった最初のきっかけは何ですか?
フリーランスになったタイミングで小学校のPTA会長の打診があり、共働きが増える中でなかなかやり手もいない時代ということもあり、「時間調整のできる私がやらなくてどうする」「誰でもできるものではないし、これは自分の役割だな」と思い、引き受けました。そこで学校運営協議会(地域と学校の協働会議)という組織にも参画したことが最初のきっかけでした。
また、私はキャリアコンサルタント試験に合格してから、接点のできた学校の先生方にキャリアコンサルタントなので「キャリア教育のお手伝いできますよ」「役に立てることがあればなんでも言ってください」と伝えていたこともきっかけが生まれた1つの要因だったと思います。
それで6年生の先生から「キャリア教育をどう進めたら良いか」という相談につながったと思います。日頃から「キャリアコンサルタントとして役に立てます」と周知していたことが後押しになったと思います。
実施したキャリア教育(1年目〜3年目)
― これまで具体的にどんなプログラムを実施してきましたか?
1年目は職業人(信用金庫・建設業など)を招集し、地域で働く人の話を聞くという座学の授業を1コマ行いました。座学だけでは楽しくないと思い、建設業ではショベルカーやフォークリフトの操作体験も実施しました。
2年目は前年度より多くの職業人を招集し、体育館でブース形式で話を聞ける「キャリアブース」と校庭での建設機材の操作体験を開催しました。パティシエ、美容師、警察、信用金庫、生命保険会社、教員、区役所など約9ブースに加え同じ地域の高校生に先輩のロールモデルとして参加してもらいました。
事前説明から本番、振り返りまで4コマの授業を行いました。3年目の今年は新たに5年生の授業も行い、6年生は期間をさらに広げ、1年間通して継続的に取り組ませていただいております。
学校現場との連携のコツと課題
― 学校と協働する際のコツや難しさはありますか?
先生は極めて多忙ですので、基本的に外部提案を受け止める余裕が限られます。最初に1時間程度の対面打合せ以外は、メールでのやり取りを中心に行っています。先生にとって打合せや電話でのやり取りなど、負担にならないよう心がけています。
2年目以降は具体的なコンテンツ案をいくつかメールで案内し、簡単な打ち合わせで内容をすり合わせ、授業内容の最終案を提示した上で当日の授業を行なっています。もちろんメールでのやり取りを中心に行なっています。一度、学校との接点が生まれれば、想像より高いハードルではありません。課題は「連絡がこまめに取りにくい」点で、催促しすぎない(先生方への配慮)をしながら進行管理することも大切かと思います。
子ども・先生の変化と効果
― キャリア教育の取り組みの手応えはありますか?
2年目以降は単発ではなく、複数回・長期間になってきているので、子どもたちはキャリア教育を身近に捉え、行動変容も見られます。もちろん授業も真剣に取り組んでくれていて、自分と向き合ったり、将来を考えたりしてくれています。
たとえば女子サッカーの進路相談(セレクション合格後の選択)で放課後に声を掛けてくれた例もありました。先生方もキャリア教育や授業内容に有用性を感じていただいておりますが、教員のキャリア教育スキルの定着はこれから蓄積されていくのかなと感じております。
今後の目指す姿・マネタイズ観
― 今後のビジョンと、持続可能性についての考えを教えてください。
今後は小中学校のキャリア教育に外部人材(キャリコン)が関わりやすい環境を作りたいと考えています。多くの方が関わるにあたり “予算化された仕組み”を行政とともに整えたいと考えていますが、個人的には「まずは役に立つこと。お金は後からついてくる。」と考えています。
ただし仲間を巻き込むには最低限のマネタイズ設計が不可欠であるとも考えています。それ以外にも金融機関向けの研修(キャリコンスキルを活かした)など、社会実装も進めたいと考えています。「小学生に伝えているようなわかりやすい言葉で大人にも響かせたい」とも感じているので、今後も説明力を磨き続けたいと思います。
メッセージ
― 最後に、これから挑戦する人へ一言お願いします。
「一歩踏み出せば、なんとかなる」。役割のヒントは自分の中にすでにあります。前を向けば応援者は必ず現れます。大切なのは、感謝と協働、そして小さくてもいい“最初の一歩”です。