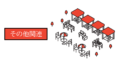本記事では「国家資格キャリアコンサルタント(以下:キャリコン)」がどんな資格で、どんな場所で仕事をして、どれくらい稼げるのか――。わかりやすくお伝えしていきます。
結論から言うと「可能性は広がるが、“資格だけで勝てる”わけではない」。
では、その理由も含めて、判断のために知っておくべき現実と選択肢を整理していきます。
1. キャリアコンサルタントって何?(簡単に)
国家資格としてのキャリアコンサルタントは、労働者や学生の「仕事・職業生活」に関する相談を受け、助言や支援を行う専門家です。試験・登録制度や受験要件は厚生労働省の案内にまとまっています。企業の人材育成や転職支援、学校の就職支援、地域支援など、相談を受ける場面は多様です。
2. 活動場所はどこ?5分類で見る現状(2023公表データ)
「活動場所」は概ね次の5つに分けられます。ここではJILPT(労働政策研究・研修機構)の調査(調査時期:2022、報告2023)を引用し、各領域の割合を示します(調査は登録者への回答に基づくもの)。数値は調査内のカテゴリに準じています。
| 活動領域 | 具体例 | 割合 |
|---|---|---|
| 企業領域 | 企業内の人事・教育、研修、配置転換相談など | 約41.7% |
| 需給調整機関/行政系 | ハローワーク、人材紹介会社、職業紹介事業所など | 約20.5% |
| 学校領域 | 大学・高専・高校の就職支援・キャリア教育 | 約20.6% |
| 地域・福祉領域 | 地域の就業支援、NPO、自治体の支援窓口等 | 約10.7% |
| その他/フリー等 | 個人相談、企業と契約した外部コンサル、フリーランス活動 | 約6.5% |
参照元:https://www.jil.go.jp/institute/reports/2023/0227.html
3. 年収はどれくらい?働き方別の目安
キャリコンの年収レンジは非常に幅があります。公的調査の分布をベースに、働き方別の目安を示します。主要根拠はJILPTの回答データ(年収分布の中央値・最頻値)および専門情報サイトのまとめです。
- 企業内(正社員):300〜700万円、中央値400〜500万円
- 行政/ハローワーク等:300〜600万円帯が中心
- 学校:公務系と同等の場合もあるがボランティアもアリ
- フリーランス:0〜数千万円まで幅広く、安定性は低い
実際の分布では、最も多かった年収帯が「300〜400万円未満」(約16.5%)、中央値が「400〜500万円未満」となっており、回答者の半数は400万円以上であると示されています。
つまり「平均的には日本の給与水準と同程度〜やや幅がある」というイメージが妥当です。
参照元:https://www.jil.go.jp/institute/reports/2023/documents/0227_01.pdf?utm_source=chatgpt.com
4. 資格だけでは稼げない?稼げる人の特徴
資格だけ持っていて仕事が勝手に来る時代ではないです。
以下の2タイプに分かれます。
資格だけでは稼げないケース
- 実務経験や相談実績が少ない
- 営業・提案経験がない
- 専門性が弱く単価競争に巻き込まれる
この場合、資格保有は“スタートライン”であるため、別の収入源(本業)で生計を立てる比率が高くなります。
稼げる人の特徴
- 企業向け高単価案件を持っている
- 特定領域の専門性がある
- 複数の収入源を持つ
- ネットワークによるリピート案件を確保
資格は信用の土台。そこに「営業」「専門性」「ビジネス設計」を掛け合わせることで初めて高収入化・独立化が現実味を帯びます。
5. 専業か兼業か──現場の実態
専業(専任・専業)で働く割合は約37%、兼業・兼任が約63%という結果(専業が約4割、兼業が6割弱)です。つまり多くのキャリコンが他の仕事と掛け持ちで活動している状況。副業・複業としてキャリアコンサルティングを活用する人が一般的に多いということです。
6. 実務スタートのステップ
もし「取得して仕事にしたい」と考えるなら、次のような切り口があるかと思います。
-
実務経験を積む場を確保する(無料・低価格の相談や社内の小さいプロジェクトで実績作り)。
-
得意領域を1つ決める(若年、ミドル、再就職、障害者支援、DXリスキルなど)。
-
提案テンプレを用意する(企業向け1枚、学校向け1枚、地域向け1枚)。
-
価格設計を決める(時間単価・パッケージ料金・顧問料を明確化)。
-
情報発信を始める(実績が増えるまではブログやSNSでの事例発信が有効)。
7. 取得判断チェックリスト
3つ以上該当すれば取得を検討する価値大。
- 企業・人事や教育領域に関心がある
- 他者の人生設計に寄り添う仕事が好き
- 営業や提案を学ぶ意思がある
- 副業・兼業としての余裕がある
- 長期的に経験を積む覚悟がある
3つ以上チェックが付くなら「取る価値あり」。0〜2なら、まずは短期の体験(ボランティアや社内業務)で“向き不向き”を確かめるのが賢明です。
まとめ
「資格=稼げる」ではありません。資格は武器の一つで、使うには
- 「キャリコンスキル(専門性)」
- 「キャリコン以外のスキル」
- 「ネットワーク」
のいずれも必要だと感じます。
一方で、企業のリスキリング需要や働き方の多様化は追い風です。戦略的に動けば、キャリコンは確実に“未来の可能性を広げる資格”になります。参考になれば幸いです。